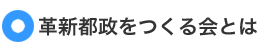連載 2020年東京オリンピックを考える(7)
2014年8月15日
曲がり角にたつオリンピック
“五輪消滅危機”
日刊スポーツ6月2日付
近代オリンピックが、ギリシャのアテネで開催されてから180年。夏季大会が30回、冬季大会が22回開催されました。
この間に、夏季大会の参加国・地域は、14から204(2012年ロンドン)に、競技は8競技43種目から26競技302種目(同)に増え、テレビ中継を通じて全世界の人々が観戦するという、世界的ビッグイベントになっています。
その一方、大会の肥大化や特定のスポンサー企業と結びついた商業主義、放映権をめぐる利権あらそい、テレビ中継にあわせた競技時間の設定、偏差なナショナリズムなど、歪みを深めているオリンピックの姿に、世界で疑問、見直しの動きがひろがろうとしています。
冒頭の記事は、2018年開催予定の冬季オリンピックに立候補を表明していたミュンヘン(ドイツ)サンモリッツ(スイス)ストックフォルム(スエーデン)などの各都市が「民意や財政難を理由に続々と辞退」。IOCが冬季大会について「存亡の危機を迎えている」として、7月の理事会で善後策を協議することとなったことを報じたものです。
実際に、オリンピックの開催経費は、ロンドン大会では当初計画の4倍近い約1兆1350億円にも達し、今年開かれたソチ五輪では5兆円以上もかかったとされ、大会の肥大化がオリンピック継続のおおきな障害になろうとしているのです。
とりのこされる国民生活
“このまま行くと平昌と東京を最後に、五輪が消滅する事態に発展する恐れも出てきた”(同)
サッカーのワールドカップが開催されましたが、開催国ブラジルでは、ワールドカップの一方で、とりのこされた国民が、「われわれの教育や医療はどこにいった」と、劣悪な住宅や医療の改善をかかげ、ワールドカップ中止を求める抗議行動がひろがりました。
ワールドカップにつづいて、2016年にリオデジャネイロで開催されるオリンピックについても黄色信号が点灯しはじめたといわれています。
これは私たちにとっても対岸の火事といってすましていられる問題ではありません。
オリンピックがアベノミクスの“第四の矢”に位置づけられ、土建国家の復活が喧伝されるその足下で、消費税増税や社会保障の連続的改悪がすすめられ、東日本大震災から3年あまりを過ぎたいまなお25万人を超える人々が避難生活を強いられ、その多くが劣悪な応急仮設住宅の生活を余儀なくされているのです。
国が1625億円もかけて新国立競技場の建設に血道を上げる一方で、東北三県の復興は遅々としてすすまず、災害復興公営住宅は計画の3・3%、わずか8百戸余り(2013年度末)しか建設されていないことに怒りの声があげられるのは当然です。
また、大会に投入される経費は、立候補ファイルに掲載されたものにとどまらず、臨海部の施設の液状化対策や土地購入費、オリンピックまでに間に合わせるとしている外郭環状道路をはじめとする三環状道路、あらたに急浮上している複数の鉄道インフラ(前号参照)、さらには、急騰を続ける工事費などを含めれば、数兆円規模の投資に膨れあがること必至です。
今年6月、IOCの調整委員会の来日を前後して、東京都は葛西臨海公園のカヌー会場をはじめ、施設計画の見直しをすすめることを明らかにしましたが、そのICO調整委員会は、「オリ・パラ都民の会」との面談にあたって、「都市をオリンピックに合わせるのではなく、オリンピックを都市にあわせるというのが、環境基準の考え方」と述べ、コーツ委員長は、マスコミのインタビューに答えて「最近、われわれの考え方に変化が起きている」「過去の五輪では、IF(国際競技連盟」の要望もあって開催国に多くを求めすぎていたのではないかと自省した」「開催都市がおおくの競技施設の新設やインフラ整備をしなければならないと感じるようではいき過ぎだ」と語りました。
その意味では、昨年9月7日に東京が2020年の開催地として選ばれたのは、安倍首相のプレゼンテーションが素晴らしかった訳ではなく、ましてや8キロメートルのコンパクトな計画が評価された訳でもなく、潤沢に資金があり、間違いなくオリンピックを開催してくれる都市としての東京を適地として選んだというのが真実ではないでしょうか。
IOC調整委員会の来日にあわせて、「オリ・パラ都民の会」が提案した施設計画の見直し提案は、まさに時宜を得たものということができます。