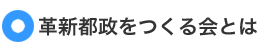首都直下地震 あらたな東京都地域防災計画を考える(5)
2013年5月15日
未体験の都市型スーパー災害
首都直下地震と東海、東南海、南海の連動地震の逼迫が指摘されています。
首都直下地震と東海、東南海、南海の連動地震の逼迫が指摘されています。
今回は、被害想定や防災計画が検証と対策をタナ上げしている大都市固有の課題、とりわけ、都市構造に着目して考えてみたいと思います。
一極集中のゆがみ
首都東京の地震災害の脆弱性の根本には、国や東京都がすすめてきた東京・都心一極集中がもたらすゆがみがあることを指摘しなければなりません。
たとえば、東京には、全国の人口のほぼ一割、1300万人が集中しており、近年の地方の疲弊・衰退のもとで東京への人口集中は加速されています。
また、東京には上場企業の本社の49・4%が集中。区部での就業者数は664万人に達しています。このうちほぼ250万人は、都外からの通勤者都民で占められています。くわえて、通勤や通学目的でない、買い物客や観光客などの往来者は京都府の人口に匹敵する約250万人にも及んでいるのです。
鉄道網の総延長も東京・広島間に匹敵する1千キロメートル、高速道路もほぼ3百キロメートルに達しています。
地震国・日本、そのなかでも地震多発地域といわれ、揺れやすい地盤構造のうえに展開する東京。その災害リスク(横浜を含む)は、ニューヨークの17倍、ロンドンの24倍にも達するもので世界の大都市のなかでも例を見ないものです。
ところが、東京都の被害想定が被害を数量的に検証しているのは、建物(家屋)の倒壊と火災延焼による被害に限られ、超高層ビルや繁華街、地下街、雑居ビル、鉄道事故などの大都市固有の被害についてはまともな検証も数値化もおこなわれていませんし、当然のように防災計画でも事実上、タナ上げとされているのです。
(1) 超高層ビル
現在、都内には、100メートルを超える超高層ビルが4百棟を超え、規制逃れの99メートルクラスの超高層ビルも30棟を超える規模となっています。このうち、石原都政以後に建設された100メートル以上の超高層ビルの床面積は新宿区の行政面積に匹敵する規模となり、石原前知事が推進した都市再生によってよみがえった“三菱村”、丸の内マンハッタン構想では、東西600メートル南北750メートル程度の丸の内の狭い地域に、16棟、延べ床面積237万平方メートルもの超高層ビルが建設され、その就業人口は24万人に至っているのです。
しかし、この超高層ビルは、長周期地震動によるヨコ揺れの危険があり、実際に、中越地震のさいには六本木ヒルズのエレベーターのケーブルが共振し破断する事故が起きていますし、東日本大震災でも大きな揺れに見舞われました。
くわえて、東日本大震災では、超高層ビルの中層階(20階辺り)で短周期地震動による破断・亀裂が発生しましたが、これはこれまで超高層ビルでは想定されてこなかった被害であり、深刻です。直下地震であった阪神淡路大震災では破断などの被害も報告されています。
日本で超高層ビルを導入するにあたって参考とされたのがニューヨークのマンハッタン島の超高層ビル群でした。しかし、一枚岩の岩盤のうえにあるニューヨークと基盤岩が1千メートルから3千メートルの深いところに沈んでいる東京とでは、地盤の強度が決定的に違います。超高層ビルは遠距離の地震の影響を受けやすく、未確定な要素がおおい建築物ということができます。
このように超高層ビルの安全性は未知数です。しかも、西新宿などの阪神淡路大震災以前に建設されたビルは、設計時に長周期地震動が想定されていず、東日本大震災後、あわてて耐震補強をおこなっている始末です。
また、幸いにして倒壊に至らなくても、エレベーターの停止、水道の断水、家具の凶器化など、住民生活と職場環境に深刻な打撃をもたらす問題が山積みで残されているのです。さらに非常用電源が地下に置かれているビルもおおく、臨海部や海抜ゼロメートル地帯では、津波の浸水で深刻な打撃を受けることになります。
まさに、未経験のスーパー都市災害への備えはまったなしなのです。